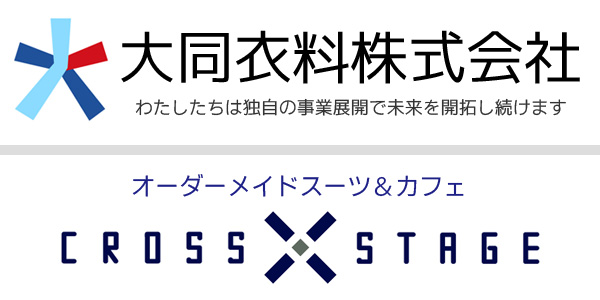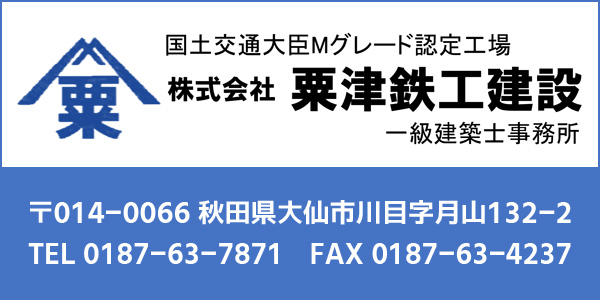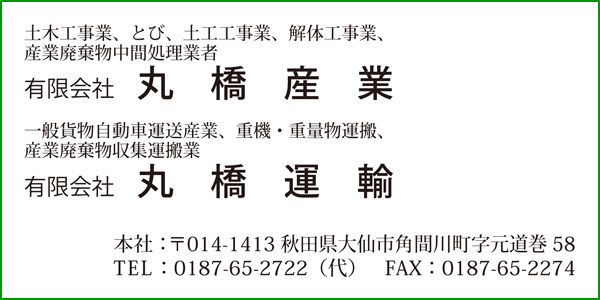旧本郷家住宅とは
角間川の隆盛を支えた明治期の秋田三大地主の一人、本郷家。その始祖は、江戸時代の元禄期(18世紀初頭)に横手市本郷地区から角間川へ移り、「能登屋市兵衛」に奉公しました。その働きぶりが認められ、現在の地に独立し、吉右衛門を名乗って本郷家を興しました。二代目が始祖の出身地にちなんで「本郷」を名乗り、以降七代にわたり「吉右衛門」を襲名しました。
明治・大正期には秋田県内屈指の大地主となり、近代の歴代当主は、いわゆる「秋田の腐れ米」の改善に取り組む秋田改良社の設立(六代の時代)や、雄物川通船貨物保険の運営など、地域の農業や経済の発展に大きく貢献しました。
家紋は「中陰蔦(なかかげつた)」です。
旧本郷家住宅概要
- 国登録有形文化財(建造物)
- 平成28年11月29日(官報告示)
- 名称:旧本郷家住宅
- 所在地:秋田県大仙市角間川町字西中上町
- 構成:主屋・文庫蔵・洋館・味噌蔵

◇ 主 屋
(写真:主屋玄関より通り土間からの全景)
明治29年(1896年)の陸羽地震で旧主屋が被害を受けたため、明治33年(1900年)に全面改築されました。主屋の各部屋には欅の良材が使用され、天井が高いのが特徴です。東側には3つの座敷が南北に並び、北側の座敷には床の間、書院、床脇が設けられています。落とし掛けには黒柿材、床柱には四方柾の秋田杉材が用いられ、床脇の天袋と地袋の引き戸には金地に松が描かれています。天井は畳大の鏡板が張られ、二重廻し縁と黒柿の格縁で仕上げられています。
また、座敷には欅材の縁と土縁が設けられています。玄関から続く通り土間は鍵状に配置され、西側の文庫蔵、南側の洋館と接続し、連続した居住空間を形成しています。

◇ 文 庫 蔵
(写真:蔵前)
慶応3年(1867年)に着工し、明治2年(1869年)に竣工した土蔵は、県内でも数少ない近世の建築様式を今に伝えています。主屋と連結する東側を除き、主屋と棟続きの覆屋(鞘屋)で囲まれた内蔵形式です。南側と西側には、蔵と覆屋の間に通路となる空間が設けられています。東西の壁面には出入口、南側には窓があります。東側の出入口には家紋と波に千鳥の透かし彫りが施され、蔵前を取り込んだ内側の壁三面には覆い板が付けられています。西側の出入口にも千成瓢箪の透かし彫りが見られます。内部の柱などの構造材には漆が塗られています。鞘屋と前室(火除け)を除いても、奥行きは約16m、面積は約130㎡(約80畳分)という非常に大きな蔵です。

◇ 洋 館
(写真:玄関側からの外観)
昭和3年(1928年)に増築されたこの洋館は、和洋折衷の様式が特徴的です。通り土間から南へ続く渡り廊下が、主屋と洋館を結びます。切妻屋根の軒を水平に張り出し、東西の壁面に設けられた出窓が目を引きます。洋館中央には廊下が通り、東側に洋室2室、西側に和室2室が配置されています。廊下の天井は蛇腹状で、メダリオン装飾が施された漆喰塗りが特徴です。
和室は、北側が8畳、南側が6畳で、間に2畳の合いの間があります。両和室には釣り床が設けられ、紫檀の束、黒檀や鉄刀木の落とし掛けなど、良質な材木が使用されています。障子の組子細工も見事な出来栄えです。

◇ 味 噌 蔵
(写真:正面外観)
大正10年(1921年)に建てられたこの建物は、東側に入口、西側に窓が設けられています。土台と床板には栗材、柱にはヒバ材、梁には杉材が使われ、屋根は置き屋根と呼ばれる構造です。外壁のモルタル洗い出し仕上げや、入口扉に使われた鋼製戸が特徴的です。
現在は主屋の北側に独立して建っていますが、戦前は調理場と棟続きでした。調理場の建物は現存しませんが、床敷石や基礎敷石が残っており、当時の様子を偲ぶことができます。

◇ 庭 園
(写真:主庭園全景)
旧本郷家庭園は、旧本郷家住宅と一体となった造園空間を形成しています。この庭園は、近代造園の祖であり、近代公園の先駆者とも称される造園家、長岡安平によって設計されました。本郷家には長岡が作成した「庭園設計図・設計書・参考図・参考書」一式が全て現存しており、近代造園史における貴重な資料とされています。
主屋の東側に配された庭門から続く日本庭園は、庭門の先が露地(茶庭)風の園地となっています。主庭園については、流れの護岸石や飛び石、石造景物の配置などに庭園設計図(長岡安平設計・大正11年)との差異が見られますが、築山の配置や流れの湧出口と流路の配置など、庭園図との共通点も見られます。