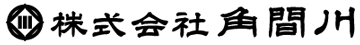雄物川流域最大の中継河港
角間川河港は、雄物川と横手川の合流点に位置し、藩政時代には雄物川流域最大の中継河港であり、横手と湯沢方面との交易拠点として繁栄しました。川の合流点にある要港として隣接する大保港と共に、土崎からの大船の終航地として重要な役割を持っていました。複数の陸路も角間川を経由しており、水路と陸路が集まる地の利で藩南部地域の一大物流拠点となり商業も大変盛んになりました。町の最盛期は明治後半頃。明治38年の奥羽本線全線開通など時代の変化により、河港は徐々にその役割を終えていきました。横手川も改修工事により旧河道は廃止され、昭和50年に埋め立てられました。現在は角間川親水公園として整備され、浜倉など往時を偲ばせる景観が残っています。
金刀比羅大神
「金刀比羅大神 明治五年 壬申五月」と刻まれています。石碑は向かって左肩から中心下方に向かって割れていて、修復された跡があります。航海の神様「金比羅権現」は、全国の船舶関係者に篤く信仰されています。雄物川筋の元の河港や船着場には、金比羅権現の神社や石碑が多くあるそうで、角間川では河港跡と愛宕神社に残っています。河港跡にある石碑は元は町中にあったもので川を埋め立てた後に、ここへ移設したそうです。
金比羅さんの石碑は、香川県の金比羅神社がある象頭山の山容が海上から三角形に見えるそうで、それを模して三角形になっているようです。愛宕神社にある「金比羅山大権現」の石碑も三角形です。
大保港
大保港は土崎からの大船の終航地として機能し、角間川港と不可分の関係でした。角間川港は横手川の合流点側にあったので、雄物川に出た辺りから400~500Mに渡って大保の船着場となっていたそうです。
上川下川の分かれ目
雄物川は角間川港辺りを境に水深が変わるため、角間川から湯沢寄りが「上川」、土崎寄りが「下川」と呼ばれていました。 そのため土崎港からの1000俵~1200俵積みの大船が入れるのは大保港・角間川港まででした。
ここから上流は浅くなるので、角間川で 500~600 俵積みの船に積みかえて鵜巣(うのす・現羽後町鵜巣地先)まで遡行、鵜巣上流は更に80俵積みの小舟に積みかえて倉内(くらうち、現湯沢市幡野地先)まで運んでいたそうです。(参考:雄物川河川整備計画書、国土交通省東北地方整備局、平成26年)
当時の米俵
久保田藩では、1俵は3斗でした。1斗は15kgなので1俵45kgです。4斗や4斗半という藩もあり、当時は統一されていたわけではありませんでした。
陸路の経由地
角間川には、大曲、六郷、横手、大雄浅舞湯沢、内小友大森本荘、各方面へ行く道が集まっています。川の水位が低く舟で荷物を運べない場合は、馬車や馬橇など陸路による物流も大いに活用されました。
舟が川を上る方法
江戸時代、川舟の上りは一般には陸岸よりの曳船でしたが、流れのゆるい所では下り同様、棹・魯・帆を適宜使用していたようです。雄物川では帆が良く利用されたようです。(参考『日本交通史辞典』丸山雍成編 吉川弘文館 2003、p233「川船」)
参考文献 【図書】
- 秋田叢書刊行会編「雪出羽道・上」『秋田叢書第5巻』秋田叢書刊行会、1933年、pp.104-113。
- 大曲市『大曲市史 第二巻 通史編』大曲市、1999年。
- 大曲市昔を語る会連絡協議会『大曲市の歴史散歩』大曲市・大曲市昔を語る会連絡協議会、1977年、pp.100-119。
- 大曲市立角間川小学校『角間川の物語』大曲市立角間川小学校、2019年、pp.1-25。
- 佐藤清一郎『シリーズ秋田の民衆史3 雄物川往来誌(上)』秋田文化出版社、1978年。
- 佐藤清一郎『シリーズ秋田の民衆史4 雄物川往来誌(下)』秋田文化出版社、1979年。