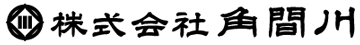昔の繁栄を今に伝える黒塀のある景色
県南有数の地主町だった角間川の繁栄を今に伝える文化財です。旧本郷家住宅と旧北島家住宅、そして旧荒川家住宅の邸宅と庭園が残り、これらの旧地主屋敷群は大仙市により整備され一般公開されています。この黒塀が続く静かなたたずまいは、昔の地主町の面影を今に伝えています。
旧本郷家住宅の主屋・文庫蔵(内蔵)・味噌蔵・洋館は国登録有形文化財となっており、建物内も見学可能です。旧北島家住宅は主屋や内蔵、外蔵など多くの建物が残り、旧荒川家住宅は豪奢な内蔵があります(北島家と荒川家は通常時非公開)。各家の趣向を凝らした日本庭園も見どころです。
また、旧本郷家住宅は令和5年には日本将棋連盟竜王戦第6局目の会場に指定され、対局は実施されなかったものの、同年12月に藤井聡太竜王(当時)が来館しています。旧本郷家住宅や三家の日本庭園は見学可能(令和7年現在は無料)で月曜定休、冬期間閉館。
旧本郷家住宅
豪雪地帯である当地方に特徴的な近代和風建築が、各時代の特色を表しながら良い状態で残っており、国登録有形文化財になっています。
- 主屋は明治33年(1900年)の建築です。主屋の各部屋には欅の良材が使用され、天井が高くとってあります。玄関から続く通り土間は西側の文庫蔵、南側の洋館と接続し、連続した居住空間を形成しているのが大きな特徴です。
- 文庫蔵は慶応3年(1867年)着工の土蔵は、県内でも数少ない近世の建築様式を今に伝えています。主屋と棟続きの覆屋(鞘屋、さや・さやおく)で囲まれた内蔵形式です。鞘屋と前室(火除け)を除いても、奥行きは約16m、面積は約130㎡(約80畳分)という非常に大きな蔵です。
- 洋館は昭和3年(1928年)の増築で、和洋折衷の様式が特徴的です。中央の廊下の東側に洋室2室、西側に和室2室が配置されています。東西の窓は出窓になっています。
- 味噌蔵は大正10年(1921年)の建築です。外壁のモルタル洗い出し仕上げが特徴的です。現在は主屋の北側に独立して建っていますが、台所棟である水屋(みずや)解体前は棟続きでした。
- 庭園は、特に主屋座敷と一体となった造園空間を形成しています。この庭園は、近代造園の祖である造園家、長岡安平によって設計されました。
旧北島家建造物
北島家住宅の建物は、主屋、文庫蔵(内蔵)、外蔵、土塀蔵(裏門)、作業小屋の5棟です。米蔵(外蔵)は解体されましたが、主屋、内蔵、味噌蔵、水屋が一棟として残っており、三家に共通する地主屋敷の典型を示し、歴史的建造物として高い価値を有しています。特に内蔵は、三家の中で唯一の座敷蔵として貴重です。通常内部は非公開です。
旧荒川家建造物
荒川家住宅および邸内の建造物は、経年劣化による損傷が著しい状態であり、公開にあたって本通りからの歴史的景観に配慮をしながら大規模に改修されました。座敷部分は、管理事務所、会議室、来訪者用トイレとしてリノベーションされました。通り土間部分は損傷が激しかったため一部を減築し、内蔵鞘屋は全面的に改築されました。内蔵は建築当時のまま保存されており、東面の黒漆喰や海鼠壁の腰壁、蔵扉の鞘飾りなど、豪奢な雰囲気を漂わせる優れた近代の土蔵建築です。内部も漆塗りで仕上げられ、質実かつ重厚な趣を伝えています。通常内部は非公開です。
黒塀
南側の旧荒川家から北側の旧本郷家まで、3軒の地主屋敷は本通り沿いに黒い板塀を廻しています。閉門した状態では、塀の内側にある地主屋敷の様子を見ることは出来ませんでした。この塀は地元では「黒塀」と呼ばれています。本通り沿いにある黒塀と、黒塀の上から覗く、地主屋敷の立派な大屋根や、枝ぶりの良い松や、紅葉の素晴らしい紅葉の景色は、角間川の町の歴史的景観となっています。
参考文献
- 大曲市『大曲市史 第二巻 通史編』大曲市、1999年。
- 大曲市昔を語る会連絡協議会『大曲市の歴史散歩』大曲市・大曲市昔を語る会連絡協議会、1977年、pp.100-119。
- 大曲市立角間川小学校『角間川の物語』大曲市立角間川小学校、2019年、pp.1-25。