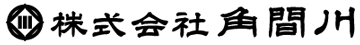古舘に佇む、朱の鳥居と白狐の社
九郎兵衛稲荷(館の稲荷)は、小野寺家臣団が移住する以前から角間川に住んでいたと記録に残る「四人百姓」の一人、高橋九郎兵衛が祀ったと伝えられる正一位稲荷社です。現在も高橋家(九郎兵衛堂さん)の氏神として大切に祀られています。かつて古舘(ふるだて)と呼ばれた地名から、「館の稲荷」とも呼ばれています。鮮やかな朱色の鳥居の向こう、手前のお社が拝殿、奥に少し離れて建つお社が本殿です。本殿の中には白狐の木像が2体で御神体をお守りしています。また、拝殿の脇には「稲倉大明神」の石碑、本殿の脇には「白専女家跡」の石碑があります。
神社の脇にはサイカチの木(地元では「しゃがじ」などと呼ばれます)があり、川を行き交う船から平鹿郡(角間川)と仙北郡(藤木)の郡境を示す目印となっていたそうです。
高橋九郎兵衛家について
今の角間川の町の形成は、慶長8年(1603)7月以降、小野寺氏旧家臣団が集団で内町に入植した所から始まります。それ以前も人々が住んでいたようですが、文書等の記録が少なく余り分かっていません。その集団入植の前の古い記録の中に、角間川に住む住人として4名の名前が確認でき「四人百姓」という呼ばれています。その中の一人が「高橋九郎兵衛」です。この人は伝承によると、慶長年間以前は「大盾の渡し守」だったとされます。今の角間川小学校のある辺りは昔「大舘」と呼ばれていたようで、「大盾」はその近くにあった横手川を金沢西根方面に渡る場所を指していると思われます。更に伝承では、高橋家は大盾の渡しだけでなく、川の目、布晒にあった渡しの元締めでもあったようです。戦国という時代からすると、この地域に一定の支配力を持った豪族から、川の渡し場という軍事的拠点を任された家だったとも考えられます。また、高橋九郎兵衛は慶長18年に浄蓮寺を開創した方でもあります。今では「百姓」というと農業という連想になりますが、伝承からの人物像はいわゆるお百姓とは異なります。
稲荷神社
稲荷神社は、五穀豊穣の神である稲荷神(宇迦之御魂神・ウカノミタマノカミ)を祀る神社であり、その眷属(神の使い)として狐、特に「白狐」が信仰されています。
白専女家跡
石塚には昭和34年建立と刻まれています。白専女(しらとうめ)は「白狐」のことです。「とうめ」は古い言葉で「老女」または「狐」を意味します。狐を「たうめ」というのは伊勢・伊賀あたりの方言とのことです(学研全訳古語辞典)。白専女家跡というのは、お稲荷さんの脇に狐の住む穴があったのでしょうか。
高橋家に伝わる話では「稲荷社の脇に高橋家の蔵があったが大正の頃に火事になって、蔵に住んで家を守ってくれていた白蛇が亡くなってしまったので昭和になってから供養のために塚を建てた」ということです。
稲倉大明神
九郎兵衛稲荷の脇に建つ明治2年建立の石碑。一見すると、稲荷と稲倉で似ていますが、「浜の稲荷」という別名のみが伝わり詳細が不明です。
調べると、鳥取県日南町にある多里神社の伝承として「稲倉大明神・(第7代孝霊天皇が)鎮座の山を御笠山という、この山孝霊天皇が稲を積せられし跡なれど、山の形稲隈の如し、此故に稲倉大明神と号す」(伯耆民談記・42頁、昭和2年)とあります。また、この神社は近世まで稲倉大明神と称されていたようです(鳥取神社庁・多里神社由緒)。この伝承から稲倉大明神は、浜倉のような米俵をたくさん積むような倉庫の守り神として信仰を集めていたのではないかと推察されます。また、石碑の「神」と刻まれている文字はえぐられた様に見えるので、明治初期の廃仏毀釈運動の影響なのかもしれません。事例の少ない神名でしたので、別途考察をまとめました。
考 察
参考文献
- 秋田叢書刊行会編「雪出羽道・上」『秋田叢書第5巻』秋田叢書刊行会、1933年、pp.104-113。
- 大曲市『大曲市史 第二巻 通史編』大曲市、1999年。
- 大曲市昔を語る会連絡協議会『大曲市の歴史散歩』大曲市・大曲市昔を語る会連絡協議会、1977年、pp.100-119。
- 佐藤清一郎『シリーズ秋田の民衆史3 雄物川往来誌(上)』秋田文化出版社、1978年。
- 佐藤清一郎『シリーズ秋田の民衆史4 雄物川往来誌(下)』秋田文化出版社、1979年。