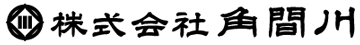悲しき歴史を秘め、静かに残る戊辰戦争の影
本町と八圭の間の橋の上流100mほどの場所には、かつて陀仏(だんぶち)と呼ばれる渦巻く深い淵があったと伝わります。慶応4年(1868)8月13日、戊辰戦争において交通の要衝であった角間川は激戦地となりました。角間川の戦いでは、奥羽越列藩同盟軍(庄内藩、仙台藩など)は、新政府軍(長州藩、久保田藩など)を圧倒。勢いに乗じた同盟軍は町に火を放ちながら新政府軍を追撃したため、退却する新政府軍、特にしんがりを務めた久保田藩兵と避難する角間川町民が川の渡し場に殺到しました。その際、同盟軍側が舟橋(川舟を繋ぎ合わせた仮設の橋)を破壊したため、川へ逃れようとした多くの人々がこの淵で命を落としたと伝えられています。親水公園には、秋田(久保田)藩士と新庄藩士を慰霊する鎮魂碑が建立されています。
鎮魂碑
激戦地だった陀仏には、この地で戦争で亡くなった秋田藩士と新庄藩士の墓十基がありましたが、昭和22年7月の洪水で川底に埋没してしまったそうです。それから45年経過した平成4年9月に慰霊のために、陀仏近くの岸の上に石碑が建てられました。願主は浄蓮寺二十四世の雲誉海龍和尚、建立者は鈴木正俊氏です。秋田藩士7名と新庄藩士3名の名前が刻まれています。
- 秋田藩 鿄 慎五郎 廿四才 甲山隊 銃士
- 仝 石川 竹治 丗二才 士分
- 仝 登坂 鶴治 廿二才 茂木秀之助家従
- 仝 長谷川 久之助 廿一才 士分
- 仝 渡部 二左衛門 四二才 仙南村前郷の人
- 仝 小松 助左衛門 五五才 半道寺卒小頭
- 仝 阿部 重左衛門 四三才 茂木隊小荷駄方
- 新庄藩 八鍬 嘉七 丗七才 銃士
- 仝仝 山科 丹治 丗六才 仝
- 仝 庄司 彦次郎 廿三才 仝
戊辰戦争
戊辰戦争(1868〜1869年)は、江戸幕府の旧勢力と明治新政府との間で起きた内戦です。鳥羽・伏見の戦いに始まり、江戸無血開城、東北・奥羽地方での会津・庄内・秋田での戦いを経て、榎本武揚らによる函館の五稜郭での抵抗をもって終結しました。新政府はこの戦争を通じて全国支配を確立し、中央集権体制の確立と近代国家への改革を推進する契機となりました。「戊辰(ぼしん・つちのえたつ)」は1868年の干支に由来します。
角間川の戦い
戊辰戦争では、秋田でも各地で戦闘が起きています。角間川周辺でも、新政府軍と奥羽越列藩同盟軍が対峙し戦闘となりました。角間川の藩士は新政府軍側です。新政府軍は、長州藩・久保田藩・新庄藩などで、奥羽越列藩同盟軍は、庄内藩・仙台藩などでした。結果は、新政府軍の戦争で亡くなった44名に対して、同盟軍は戦争で亡くなった者は0名と、奥羽越列藩同盟の圧勝に終わりました。8月13日は正午頃、角間川に陣取る新政府軍に対し、大雄の田村から列藩同盟軍が進行し攻撃を開始。同盟軍・庄内藩の進撃で新政府軍・久保田藩を圧倒し、戦闘は2時間程度で終わりましたが、町は家屋を燃やされるなど大きな被害が出ました。
久保田藩
久保田藩(くぼたはん)は、現在の秋田県を領地としていた藩で、一般には「秋田藩」とも呼ばれます。関ヶ原の戦いを経て、常陸国(現在の茨城県)から移封された佐竹氏が藩主を務め、幕末まで約270年にわたって藩主を務めました。
佐竹義宣が秋田に入国した際、当初は旧領主・秋田氏の居城であった湊城(現在の秋田市土崎港)に入りました。しかし、湊城は日本海に面しており、防衛上の問題や、大規模な城下町を築くには不向きでした。そこで、義宣は内陸部の神明山に新しい城を築くことを決意しました。この地が「窪田(くぼた)郷」と呼ばれる場所だったため、築城した城を久保田城と名付けました。江戸時代の藩は、藩庁である居城の名をもって藩名とするのが一般的でしたので、新しい居城である久保田城の名を冠して「久保田藩」と称しました。
明治維新後の明治4年(1871)に、藩は政府に対して藩名の変更を願い出ました。その理由として、「久保田」という地名が元々小さな村の名称に過ぎないのに対し、「秋田」という地名は古くからこの地方全体を示す呼び名であり、よりふさわしいという考えがあったようです。この願い出が認められ、正式に藩名が「秋田藩」に改称されました。
角館を居城とした戦国武将、戸沢家の子孫
新庄藩は、最上郡全域と村山郡の一部を所領とし、江戸時代初めより戸沢氏が藩主を務め、約250年間、11代にわたって続きました。戸沢氏は、もともと鎌倉時代以来、出羽国に勢力を広げた名門で戦国時代には角館を居城とし、戸沢盛安の代に勢力を拡大しました。盛安は別名「夜叉九郎」「鬼九郎」と称されるほど勇猛な武将として名を馳せました。また戸沢氏は、横手を居城とした小野寺氏と所領を接する存在でした。江戸時代に入り、元和8年(1622年)に山形藩最上氏が改易された後、関ケ原の合戦後に常陸松岡藩主となっていた盛安の子、戸沢政盛が新庄藩6万石の藩主として入封しました。
戊辰戦争では、当初、奥羽越列藩同盟に参加しましたが、その後同盟を離脱し、新政府軍側に与しました。このため、慶応4年(1868)7月の旧幕府軍との間で激しい戦いが行われ(新庄の戦い)、新庄城は一時、旧幕府軍の庄内藩によって占領されるなど大きな被害を受けました。その後は秋田藩内に一時的に逃れ、8月には角間川の戦いに新政府軍として久保田藩と共に新庄藩の部隊が参加しています。新庄城跡は現在、最上公園として整備されており、桜の名所として知られています。
参考文献
- 大曲市『大曲市史 第二巻 通史編』大曲市、1999年。
- 大曲市昔を語る会連絡協議会『大曲市の歴史散歩』大曲市・大曲市昔を語る会連絡協議会、1977年、pp.100-119。
- 佐藤清一郎『シリーズ秋田の民衆史3 雄物川往来誌(上)』秋田文化出版社、1978年。
- 佐藤清一郎『シリーズ秋田の民衆史4 雄物川往来誌(下)』秋田文化出版社、1979年。