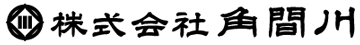高橋九郎兵衛が草創と伝わる寺院
浄土宗の寺院。ご本尊は阿弥陀如来。当寺は高橋九郎兵衛が宿念を遂げ、御仏に帰依して慶長18年(1613)、大曲の本誓寺第2世三誉上人を招請して開山を仰ぎ、自ら願主となって浄蓮寺を草創したと伝わります。令和7年9月には、同寺開山三誉上人の四百年忌にあたり絹本著色當麻曼荼羅図が特別に一般公開されました。また、境内には古い板碑があり、鎌倉末期~南北朝初期のものとされています。
絹本著色當麻曼荼羅図
浄蓮寺には国指定重要文化財「絹本著色當麻曼荼羅図(けんぽんちゃくしょくたいままんだらず)」(昭和25年8月指定)が伝わっています。非公開です。この曼荼羅は「綴織當麻曼荼羅図」(奈良時代・国宝・奈良當麻寺)の4分の1サイズの模写とされ、「鎌倉初期か中期の作品」と推定されています。大きさは縦137.5㎝、幅123.5㎝です。浄土宗の宗宝にも指定(令和3年2月)されています。色彩も未だ鮮やかで、繊細な筆使いも見て取れます。
この曼荼羅図は、宝暦年中(1751~1763)、角間川の北島三左衛門長好がお伊勢参りの際に京都の寺院(透玄寺と伝わります)で買い求め、浄蓮寺に寄進したものです。曼荼羅の裏面に「恵心僧都の真蹟、當麻曼荼羅、横四尺五分、竪四尺五寸、右北島三左衛門宝暦年中、これを京都に得て当寺に寄進する所也、其の由来する所は洛陽透玄寺還誉贈る所の書これを詳らかにす」(注:原文は漢文です)と書いてあります。
「當麻曼荼羅図」は、浄土宗において重要な経典である『観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)』に説かれる極楽浄土の荘厳な様子や、人々が極楽に往生するための瞑想の様子などを、絵画として具体的に表現しています。中央に広大な極楽浄土の様子が描かれ、その周囲に『観無量寿経』の物語や教えが図解されています。無量寿とは阿弥陀如来のことです。
宝暦年中のいつ買い求めたか
他の記録も合わせて考えますと、宝暦年中に北島三左衛門長好がお伊勢参りに行ったのは「宝暦3年(1753)」ではないかと、筆者は考えています。
當麻曼荼羅について
浄蓮寺の當麻曼荼羅図は、観経曼荼羅(かんぎょうまんだら)という浄土教系のものです。中央の大きな枠は「玄義分(げんぎぶん)」といい、阿弥陀三尊(阿弥陀、観音、勢至)を中心に多くの菩薩や極楽浄土の様子が描かれています。左側の縦の枠は「序分義(じょぶんぎ)」といい、インド摩訶陀国の王舎城の韋提希夫人(いだいけぶにん)とその子供の阿闍世王(あじゃせおう)の悲劇説話が描かれています。左下から上の方へ、1コマ毎に説話の場面が展開していきます。釈尊(お釈迦様)が韋提希夫人に観無量寿経を説き聞かせるまでが描かれているそうです。右側の縦の枠は「定善義(じょうぜんぎ)」といい、釈尊が韋提希夫人に説いた、阿弥陀如来の極楽浄土と極楽へ往生する方法が描かれています。下段の中央の枠は「縁起段」といい、浄蓮寺のものは黒くなってしまっていますが、ここは曼荼羅の由来が書かれた銘文が記されている枠だそうです。縁起段の両脇の枠は「散善義(さんぜんぎ)」といい、九品往生(くほんおうじょう)という上品上生(じょうぼんじょうしょう)から下品下生(げぼんげしょう)までの9段階の往生の有様が描かれています。
板碑
鎌倉末期~南北朝初期のものと推定されている板碑です。昭和47年10月に、高橋九郎兵衛家墓所に埋まっていた状態で見つかりました。板碑は摩滅が酷く良くは見えませんが梵字が刻まれてあるそうで、お寺のお話によると「大日如来」を表すものだそうです。大日如来は真言密教の仏様になりますので、浄土宗の浄蓮寺が建立されるより前の時代のものと思われます。
参考文献
- 秋田魁新報社企画部『秋田のお寺 大曲・仙北』秋田魁新報社、1978年、pp.126-127。
- 秋田叢書刊行会編「雪出羽道・上」『秋田叢書第5巻』秋田叢書刊行会、1933年、pp.104-113。
- 大曲市昔を語る会連絡協議会『大曲市の歴史散歩』大曲市・大曲市昔を語る会連絡協議会、1977年、pp.100-119。
- 大曲叢書編纂会『大曲叢書6 国指定重要文化財 浄蓮寺当麻曼荼羅』秋田民報社、1975年。
- 大仙市教育委員会『重要文化財 絹本着色當麻曼荼羅図(パンフレット)』大仙市教育委員会。