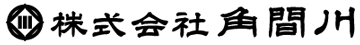小野寺氏ゆかりの寺院
真宗大谷派の寺院。ご本尊は阿弥陀如来。棟高のどっしりした本堂は威容を誇っています。戦国武将小野寺義道の弟で大森城代の小野寺孫五郎康道の発願により、文禄3年(1594)に開創と伝わります。5代目住職善雅法師が元禄3年(1692)に本願寺より親鸞聖人御絵像など伝授され現在の寺の礎を築きました。菅江真澄『雪の出羽路』(1822)には「開祖大森ノ郷に住居せしゆえ大森を以て山號とせり」と記述があります。尚、小野寺康道は関ケ原合戦後、小野寺氏改易により兄の義道と共に石州津和野(石州は今の島根県西部)に配流となったと伝わっており、寛永18年(1641)没しています。
小野寺孫五郎康道
小野寺康道は、大森城を居城としたことで「大森五郎」とも呼ばれます。兄である戦国大名・小野寺義道を支え、小野寺氏の重要な一翼を担った武将であり、特に武勇に優れていたことで知られています。康道は天正年間(1573~92)に大森城主となり平鹿西部地方一帯を支配します。大森城は天正18年(1590)の豊臣秀吉の奥州仕置の際に、上杉景勝が検地を行う拠点とするなど当時のこの地方における重要拠点でした。 慶長5年(1600)の関ヶ原合戦の際、小野寺氏は西軍の上杉氏に与したため、同年10月、最上氏・秋田氏・由利郡諸氏の連合軍1万余りに大森城を攻められました。小野寺方の手勢の数は明らかではありませんが、山城の利を生かし籠城、奮闘したと伝わります。しかし後詰軍が着陣した連合軍に対し、ついには大森城を開城することになったようです。その後、小野寺氏は改易、康道は兄義道と共に石見国津和野(現在の島根県)の坂崎家に預けられる身となり、寛永18年(1641年)に津和野で没したと伝えられています。小野寺康道は、兄の義道をよく支え、小野寺氏の勢力の一翼を担った武勇に優れた武将でした。
参考文献
- 秋田魁新報社企画部『秋田のお寺 大曲・仙北』秋田魁新報社、1978年。
- 秋田叢書刊行会編「雪出羽道・上」『秋田叢書第5巻』秋田叢書刊行会、1933年、pp.104-113。
- 大曲市昔を語る会連絡協議会『大曲市の歴史散歩』大曲市・大曲市昔を語る会連絡協議会、1977年、pp.100-119。
- 佐藤清一郎『シリーズ秋田の民衆史3 雄物川往来誌(上)』秋田文化出版社、1978年。
- 佐藤清一郎『シリーズ秋田の民衆史4 雄物川往来誌(下)』秋田文化出版社、1979年。
- 半田和彦「角間川給人の系譜」『秋田藩の武士社会』無明舎出版、2006年、pp.13-50。