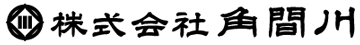角間川給人の総鎮守神社
角間川の町の東側、内町と呼ばれる地区の南端に鎮座しています。慶長10年(1605)頃の建立と伝わる、この地に移り住んだ小野寺氏と所縁深い角間川給人の総鎮守神社です。
横手平鹿一帯を所領とした横手城主小野寺義道は、慶長5年(1600)の関ケ原の戦いで「主命に従わず」として、慶長6年(1601)に徳川家康により改易されたうえ石見国津和野に預けとなりました。残された小野寺家旧臣たちは相談し、常陸から転封されてきた佐竹氏に仕官を願い出て角間川の開発を許され70余名がこの地に移り住みました。その頃には小野寺氏のかつての本拠地だった沼館城内の八幡神社も戦乱で荒廃しており、旧臣達がこれを見かねて角間川に勧請し産土神として祀ったと伝わります。沼館の八幡宮は源頼義・義家と縁の深い神社であり、内町の八幡宮はその流れを汲むことになります。御祭神は誉田和気命(ほむたわけのみこと)、例祭日は9月15日です。
境内には馬頭観音様のお堂と、和光殿があります。また、社殿北東の裏手には、喜福院の墓地があります。これは昔、八幡神社の東側に喜福院があった名残です。なお、菅江真澄は八幡宮の末社に、稲荷神社と毘沙門天王ノ社があったと記録しています。
御祭神
誉田和気命(ほむたわけのみこと)は、応神天皇(誉田別尊)として知られています。武運の神、厄除けの神、安産・子育ての神として信仰されています。
馬頭観音様
八幡社の南側にお社があります。元は大浦町在住の方が別当としてお祀りしていたそうで、後に八幡神社の境内にお祀りすることになりました(合祀ではありません)。馬は生活に欠かせないものとして、特に武士や農民にとっては重要な存在であり、馬の供養や安全を祈願するため信仰されました。当地ではそれに加えて、河港関係で物資の運搬等に従事した馬の守り神としても信仰された面もあっただろうと思われます。現代では無病息災、厄除け、交通安全、ペットの健康と安全など、様々なご利益があるとされています。
菅江真澄・雪の出羽路の記述
「給人坊(うちまち)に社あり。八幡宮、座(ませ)り。ここ武家町(うちまち)はみな小野寺の臣達(おみたち)なれば、昔在りし世をいただきまつりし、沼館の若宮八幡宮を此地にうつし奉る。此御神はいにしへ箭神山にませし御神ながら、小野寺城中うつし奉りしを、落城の後にここにもしかうつし奉るといふ。※1)」
※1)秋田叢書刊行会編「雪出羽道・上」『秋田叢書第5巻』秋田叢書刊行会、1933年、p.105
この中の「箭神山にませし御神」というのは横手市雄物川町矢神にある矢神八幡神社のことで、沼館八幡神社の元宮。矢神八幡神社は永延2年(988)に京都の男山八幡宮の分霊を勧請創建。元は弓矢神八幡といわれ、前九年の役(1051-62)に源頼義・義家父子が戦勝を祈願、延久年間(1069-74)に源義家が社殿を造営したと伝わります。
戦国大名小野寺氏
戦国時代には、出羽国仙北三郡(雄勝郡、平鹿郡、仙北郡)を中心に、由利郡・河辺郡・最上郡にまで勢力を広げた戦国大名。改易される前、当主の小野寺義道は横手城を本拠としていました。
大青面金剛供養塔
→見当たらず(2025年6月25日現地調査) 元禄2年(1689)3月建立、建立者は芦田茂右衛門、佐貫五郎兵衛
庚申信仰に関連する石塔、祭神が青面金剛
昭和21年内川(横手川)の改修工事により八幡社東裏の墓地に移転(大曲市の歴史散歩)とのことだが、現地で発見できず。現地調査継続。
参考文献 図書
- 秋田叢書刊行会編「雪出羽道・上」『秋田叢書第5巻』秋田叢書刊行会、1933年、pp.104-113
- 大曲市『大曲市史 第二巻 通史編』大曲市、1999年。
- 大曲市昔を語る会連絡協議会『大曲市の歴史散歩』大曲市・大曲市昔を語る会連絡協議会、1977年、pp.100-119
- 大曲市立角間川小学校『角間川の物語』大曲市立角間川小学校、2019年、pp.1-25。
- 「角川日本地名大辞典」編纂委員会・竹内理三『秋田県地名大辞典 5秋田県』角川書店、1980年、p.651
- 半田和彦「角間川給人の系譜」『秋田藩の武士社会』無明舎出版、2006年、pp.13-50。
参考文献 新聞記事・ウェブページ
- 秋田の神社検索.秋田県神社庁ホームページ.(2025年6月19日閲覧)
- https://akita-jinjacho.sakura.ne.jp/tatsujin_etc/01_jinja/finder.html