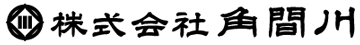児童公園(角間川小学校四上校舎跡)
角間川保育園の西側にある公園ですが、昔この辺りは角間川小学校があった場所です。一部が大曲農業高校定時制の校舎だった時もあったそうです。
明治5年(1872)頃、覚善寺南方の小中島に講学所(漢学塾舎)がありました。戊辰戦争で校舎を焼失し喜福院に間借りしていた郷校(士族学校)と合併した後、明治7年(1874)に小中島学校と改称し創立されました。明治16年(1883)に角間川小学校と改称され、明治32年(1899)に小中島から四上町に移転しました。その四上校舎があった場所が現在の、角間川公民館・角間川保育園・角間川児童公園のある場所です。昔の木造校舎の一部(体操場と称されていた部分)は角間川剣道場として令和7年現在も使用されており、児童公園の入り口脇には旧角間川小学校の門柱が残っています。
角間川郷校
郷校(ごうこう)というのは、秋田藩の藩校明徳館の直営の分校としての性格を持っている学校のことです。角間川郷校は文久元年(1861)に内町の中村町に開設されています。この角間川郷校の経費については、設立から文久3年までは、角間川出身の学者である関口兼三の献納によって賄われていたことが記録に残っています。文久4年からはかつて組下として角間川給人を配下においていた梅津小太郎が20石を寄付して学校経費としているようです。
関口兼三
関口兼三は文化8年(1811)生まれ。天保11年(1840)、29歳の時に江戸に出て、高名な安積艮斎の塾で学び始めます。この安積艮斎は幕府の儒者を拝命し、幕府の最高学府である昌平坂学問所の教授となった当時トップクラスの儒学者です。兼三はこの安積門下において塾頭にまで昇りつめた秀才であったようです。安積門下生には著名な人物が多く在籍しています。木戸孝允、吉田松陰、高杉晋作、岩崎弥太郎、前島密などが、それぞれ在籍時期は異なりますが、安積艮斎の元で学んでいたそうです。そのような中で、兼三は一時期、塾頭を務めたというのは、かなりの学識と人望を備えた人物であったと思われます。
その後、兼三の学識が素晴らしいことを知った藩の家老で角間川組下の梅津氏によって、秋田に戻り藩校の教授となることを要請されます。兼三の再三の辞退にも関わらずついに説得され、安政元年(1854)に秋田に戻り明徳館教授となりました。しかし、文久元年(1861)明徳館の教授を辞して角間川に戻ったそうです。角間川に戻った兼三は、同年、私費を投じて学校を開設します。島森氏資料では、この学校を青松館としています。
明徳館教授を辞めて角間川に戻った年に兼三の寄付によって作られた学校は、角間川郷校なのか私塾(青松館)なのか?という事ですが、筆者は、兼三が文久元年に作った私塾が、後に藩から郷校として認められたのではないかと推察しています。
講学所
明治5年(1872)、角間川の地主で貴族院も務めた最上広胖氏など外町の有志が資金を出し合い講学所を設立、校舎を新築しました(傳習学校とも呼ぶ)。講学所には寄宿舎の設備もあり、平鹿、仙北はもとより大館、能代、秋田、亀田等よりも来学するほどでした。(尋常高等小学校郷土史年表)
明治7年(1874)4月7日、小中島漢学塾舎(講学所青松館)を小中島学校と改称し創立、教師2名、児童90名でした。同年5月、門の目村に雄東学校創立(布晒分校前身)、児童31名でした。
青松館
青松館と呼ばれた学校はどの学校だったのか、資料によって一定ではありません。関口兼三が開いて後に郷校となった学校、地主たちが開設した講学所、郷校と講学所を合併させた学校(漢学塾舎?)、この3つの内のいずれかが青松館と呼ばれていたのだろうと思われます。
参考文献
- 大大曲市『大曲市史 第二巻 通史編』大曲市、1999年、pp.211-222。
- 大曲市立角間川小学校「文武不岐 百年の歩み」大曲市立角間川小学校、1974年、pp.10-17。