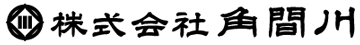小野寺家旧臣の集団入植の地
角間川は在郷町でありながら、町東側の内町(侍町)と西側の外町(商人町)という町割りは大仙市内では特徴的です。家の地割も異なり、内町は間口が広く、外町は奥行きがあります。秋田藩下で内町と言えば士族の住む町を指します。ここに内町ができたのは、菅江真澄翁も記録しているように小野寺家の旧家臣団が集団で移り住んだからです。内町の通りは「鉤型(かぎがた)」の形状で、敵侵攻時に見通しを効かせず進軍速度を落とす工夫と言われます。
角間川給人
給人というのは、秋田藩では藩主直属の家臣(直臣)で、藩政の実務を担当した武士たちのことです。秋田藩は「地方知行制(じかたちぎょうせい)」で、これは藩主が家臣に土地を与え、そこから年貢を徴収する制度の事です。この土地を知行地(ちぎょうち)や給地(きゅうち)といい、給地を与えられた家臣を「給人(きゅうにん)」と呼びました。角間川にまとまって配置された小野寺旧臣達は、藩主直属の武士団となりましたので「角間川給人」と呼ばれています。
この角間川給人に与えられた土地(百万刈輪)は、開墾しなければならない原野で、誰かが既に作ってくれた圃場などではありませんでした。よって、水田に水を引く用水路工事から始めなければならない「新田開発(しんでんかいはつ)」に入植直後から取り組んでいます。しかも角間川給人は、給人自らが土地を開墾し耕作するという特殊な形でした。刀を鍬に持ち替えて苦労して新田開発にあたり、角間川開と呼ばれる美田を作り上げました。開発初期の頃は収入が無いので、横手川で獲れる鮭を売って収入にしていたようです。
松岡宅兵衛常伸答申書
明治十四年(1881年)秋明治天皇御巡幸に際し、管内事情奏上のため縣令石田英吉へ「角間川の士族について」と題して日野哲之進を介して諮問せられ、当町士族の碩学松岡宅兵衛常伸が答申したものです。最も近代の記録であり、しかも内町の全貌を実に要領よく取りまとめた代表的な記録とされています。
以下答申書記録内容
「元禄七年(※1)二月十日高九百四十八石一斗八升の判紙惣給人七十六人へ下され候元角間川士族共七十六戸有之候處、追々逐電(※2)或は家跡断絶にて当今六十五戸何れも小野寺家普代の士(※3)或は鎌倉将軍旗下の士にて流落小野寺へ身を托し、又は由利十二頭の子孫にて士類にあらざる者一人も無之候。
慶長の夏(※4)角間川へ引移り候節は當町の士族屋敷は荒蕪の地(※5)にて居住の者一人も無之候へ共その以前に於ては人家ありたると見え当今大舘町といふ所に古舘の跡有之大舘町と浦町との間に明和の年中迠(※6)城の濠の形あり水鳥など遊び居たりとなり。大舘古城北側より仙北郡金沢西根に通ずる路あり。ここに橋ありて大舘橋といふ。この所にて戦ありたることは奥羽軍記に見えたり。その路の東に小堰あり一本橋かかりて両傍葦原なりと今は内川にて 巾五六十間の川なり角間川入口の橋の架りたる十丁位の上流なり。大舘の城跡は?(※7)の居たるか名は傳らず。当町中村町と称する士族屋敷は元寺院跡と見え川欠の所より火葬場の灰と銭と出たることあり。又金佛も出たることありその隣は鍛冶屋敷と見え金屑出土せることあり。角間川は慶長の頃四軒の人家ありたり(※8)と傳えられ士族開墾にかかりたるより諸方より烏集して一村を成せり。」
- ※1、元禄→1688-1704 元禄七年は1694年
- ※2、逐電→ちくでん。逃げて行方をくらますこと。
- ※3、普代の士→譜代の臣、代々同じ主家に仕える家系。
- ※4、慶長→1596-1615、角間川給人の移住は慶長八年七月(1603年)
- ※5、荒蕪の地→荒れ果てて雑草の茂るがままになっている土地
- ※6、明和→1764-1772。「迠」=迄、まで。
- ※7、?→漢字1文字、判読できず。
- ※8、四人百姓として伝わる。
現代語訳
元禄7年(1694)2月10日、高948石1斗8升の判紙(=石高に応じた給紙)が、合計76人の給人に下された。 もともと角間川の士族は76戸あったが、次第に去って行方知れずになったり、あるいは家が断絶したりして、現在は65戸となっている。これらはいずれも小野寺家の代々の家臣であり、あるいは鎌倉将軍家の旗下の士が流れ落ちて小野寺家に身を寄せた者、または由利十二頭の子孫で、武士以外の者は一人もいない。 慶長の頃(1596–1615)、角間川へ移り住んだ当時は、この町の士族屋敷は荒れ果てた原野で、住んでいる者は一人もいなかった。しかしそれ以前には人家があったらしく、今「大舘町」と呼ばれる所に古城の跡が残っている。大舘町と浦町との間には、明和年間(1764–1772)頃まで城の堀の跡が残っていて、水鳥などが遊んでいたという。
大舘古城の北側からは、仙北郡金沢西根へ通じる道があった。そこには橋がかかっていて「大舘橋」と呼ばれていた。この場所で戦があったことは『奥羽軍記』に記されている。その道の東には小さな堰があり、一本橋がかかっていて両側は葦原で、今では内川(訳者注:横手川のこと)となり、幅50〜60間(約90〜110m)の川になっている。角間川の入口の橋がかかっている場所から、およそ十町(約1km)上流にあたる。 大舘の城跡には、誰が居たのか名は伝わっていない。
また、当町の中村町(訳者注:荒川医院のある通りの辺り)と呼ばれる士族屋敷は、もとは寺院の跡と見え、川崩れの際に火葬場の灰や銭が出てきたことがある。さらに金仏が出土したこともある。その隣は鍛冶屋敷だったらしく、金屑が出土したことがある。
角間川は、慶長の頃には4軒の人家があったと伝えられる。それを士族が開墾に取りかかり、やがて各地から人々が烏の群れのように集まってきて、一つの村を成したのである。