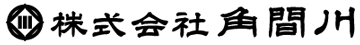町を見守る、大きな守り地蔵
上町の道端にお堂があり、その中に南東の方を向いて立つ身の丈2.2メートル、台座も含めると3.4メートルもある大きなお地蔵様がおります。この場所の土中より2体の地蔵尊が見つかった為、2体の地蔵尊の御霊をひとつにまとめ文政7年(1824)建立されたそうです。今もお堂の中に3体並んでいます。この辺りはかつての町はずれで、下の地蔵さんと町の両端に地蔵を祀り、町内安全と無病息災を願ったのではないかと伝わります。北前船の帰り荷として運ばれた石で作られたと伝わり、その石は大阪城の石垣と同じ小豆島の石だということです。
二十三夜塔
上のお地蔵さんのお堂の中、左側にあります。二十三夜塔(にじゅうさんやとう)とは、月待塔(つきまちとう)のひとつで、特定の月齢の夜に集まり「月待ち」という月を拝む行事を行った民間信仰です。二十三夜塔は、一般には勢至菩薩を本尊として祀る「二十三夜講」という講中で、旧暦の23日に月の出を待ちながら飲食を共にし、その記念や供養のために建てられたと言われています。
弁財天様の掛け軸
二十三夜塔の上に掛けられています。丸くふくよかな顔、穏やかな雰囲気を纏いつつも引き締まった表情、鮮やかな色彩の宝冠と豪華な衣装で手に琵琶を持ち、蓮華座に坐っています。また御尊顔の後ろに円光という光背が描かれていることから、弁財天の絵と思われます。掛け軸の痛みや絵のシミはあるものの、繊細な筆使いで見事な弁財天像が描かれています。特に全体の雰囲気は柔和で親しみを感じさせつつも、眉、目元、口元の引き締まった印象から威厳も感じさせる描き方が見事です。琵琶を持つ手や指先も柔らかに写実的に描かれ、奏でる音が聞こえてくるような自然な琵琶の持ち方も秀逸です。宝冠や衣も非常に繊細かつ鮮やかに描かれており、美術館にあっても違和感のない素晴らしい弁財天像だと感じます。是非、お地蔵様に手を合わせつつ、弁財天様にも会いに行ってみてください。
砂虱除碑
上の地蔵さんの向かって右脇にある「砂虱除(ケダニヨケ)※」の石碑。石碑の表には「元治二年 砂虱除 講中安全」と刻まれています。元治2年は1865年です。秋田の方言で「ケダニ」とは、恙虫(つつがむし)を意味します。この恙虫を媒介とする感染症は、信濃川(新潟県)・最上川(山形県)・雄物川(秋田県)周辺で特にみられる風土病とされ、感染すると強い頭痛・倦怠感・高熱等の症状が現れ、治療法もなく命に係わる病として、雄物川中流域一帯の住民や通行人に大変恐れられてきました。角間川は特に河原周辺で働く人も多かったはずで、この石碑も虫除け祈願のために建てられたものと思われます。近くでは大雄阿気にケダニ地蔵があります。
※「砂(沙)虱」は「さしつ・すなじらみ」と読みますが、菅江真澄翁も「沙虱(けだに)」と読ませていますので、それに倣いました。
己巳(つちのとみ)塚
砂虱除碑の隣りにある石碑。この石碑の縁起は調査中ですが、巳(蛇)は弁財天の使いとされて、60日ごとに巡ってくる「己巳の日」は弁財天のご縁日とされています。地蔵堂の中には弁財天様の掛け軸がありますので、弁財天信仰に関係があるかと思われます。
ケダニ治験に功績のあった地元の医師・大友玄圭
大友玄圭は八沢木で保呂羽山波宇志別神社の神職一族の家に1776年に生まれました。角間川で医師をする養父大友道円吉政を継いで、玄圭も角間川で医業を行いました。文化13年(1816)頃、雄物川周辺で発生する風土病の原因が「ケダニ(ツツガムシ)」であることを発見し、治療法の研究をしました。文政2年(1819)にケダニによる症状と治療法をまとめた上申書「計多仁治験」を藩公佐竹義睦に提出しています。1828年没。
また、玄圭の子、大友玄宰は父を継承しケダニの研究に従事しました。米沢藩でケダニ多発の折、秋田藩に治療法の照会があり、父玄圭の研究と自身の研究成果である外科的治療法を付け加えた報告書を藩に提出し、米沢藩より褒美を受けています。 現在は治療法は確立されていますが、ワクチンなどの予防策は開発されていません。
菅江真澄の沙虱(ケダニ)の記録 原文
「河隅川(ここにて内川といふ)をさかのほれば笹巻キといふ処あり。そこにいといと大なる蛇すみぬといへり。をりとして見る人あり。そのわたりは沙虱(けだに) ありて、人をさせはしぬもの多し。此沙虱(けだに)てふものは蛇の身に付ク虫にやあらむといへり。雄勝、平鹿、仙北にもあるよし、こと国にもあるにや。信濃川の流の末にもありて、越後の国にては嶋虫と云ひまた恙ノ虫ともいへり。此虫雄勝ノ郡逆巻といふ処にむかしはいといと多かりしが、今はしからず、御膳川(おものがわ)の末にのみいたりぬ。ここの笹巻、逆巻、名も能ク似たる川の辺なり。¹⁾」
1)秋田叢書刊行会編「雪出羽道・上」『秋田叢書第5巻』秋田叢書刊行会、1933年
菅江真澄の沙虱(ケダニ)の記録 現代語訳
「河隅川(ここでは「内川」と呼ばれている)をさかのぼっていくと、笹巻という場所がある。そこには、たいへん大きな蛇が住んでいたと伝えられている。ときおり、その姿を見たという人もいる。そのあたりには沙虱(けだに)という虫がいて、刺されると命を落とす者が多い。この沙虱(けだに)という虫は、蛇の体につく虫ではないかとも言われている。雄勝、平鹿、仙北の各地にもこの虫がいるといい、ほかの国々にもいるのだろうか。信濃川の下流、越後の国でも見られ、嶋虫(しまむし)とも恙の虫(つつがのむし)とも呼ばれている。この虫は、かつては雄勝郡の逆巻(さかまき)という場所にたいへん多くいたが、今ではそうでもなくなり、御物川沿いのその少し下流の辺りにしか見られなくなっている。この笹巻と逆巻は、名前もよく似ており、どちらも川辺にある土地である。」
ケダニの祠
新町の稲荷神社から見て西の方、バイパスを越えて堤防の手前、田んぼの中に数本の木立が見える場所に、ケダニ関係と思われる祠がある。手前に三角の石碑もある。
参考文献
- 大曲市昔を語る会連絡協議会『大曲市の歴史散歩』大曲市・大曲市昔を語る会連絡協議会、1977年、pp.100-119。
- 児玉栄一郎「大友玄圭と「沙虱毒治験」について」『秋田県衛生科学研究所報』第11号、昭和42年、pp.182-191。