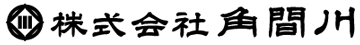神子を埋葬した伝承の残る塚
木内へ向かう沼館街道の西側にある塚で、石碑には「旭塚」、「文政五壬午(1822年)七月七日 黒丸惟孝建之」と彫刻されています。塚は、元々街道東側にあったものが道路改修(昭和時代か)によって現在地に移されたとのことです。 旭塚には伝承があり、菅江真澄の『雪の出羽路・平鹿郡』に記録されています。旭塚の記述部分を以下に抜粋します。
出羽路の原文
旭塚というあり。いつのころならんか、朝日ノ神子という行い尊きみこあり。いまだ身は老ともならされど、吾れ思う事あり神となりて民衆を守らん、穴を掘り塚にこめてよと人々に頼めば、よしある事ならんとて みこの願いのままに埋めたりという。近き世まで塚の内に鈴の音 聞えしという。¹⁾
1)秋田叢書刊行会編「雪出羽道・上」『秋田叢書第5巻』秋田叢書刊行会、1933年、pp.110-111
現代語訳
旭塚(あさひづか)という塚がある。いつの時代のことかははっきりしないが、「朝日の神子(みこ)」と呼ばれる、たいへん徳の高い巫女(または神職の女性)がいた。その神子は、まだ年老いてはいなかったが、「私は心に思うところがある。神となって、人々を守る存在になろう」と決意し、人々に「私を塚に納めてほしい、穴を掘って埋めてくれ」と頼んだ。人々は「何か深い意味があるのだろう」と考え、神子の願いのままにその身を塚に埋めたという。そして、つい最近の世まで、その塚の中から鈴の音が聞こえていたのだという。 菅江真澄の記録では、お盆8月13日の夜、肝煎(町や村など集落の長)が裃(かみしも)を着てお参りをしていた、ということです。
神女境内(みこやしき)
なお、菅江真澄の角間川村の項のうち、「給人町(うちまち)」にあった「神女境内(みこやしき)」という屋敷(または場所)について以下のように記しています。
(原文)「士坊(内町)新町に在り。そのゆえよしさだかならねど、人のものがたりのまにまに旭塚のくだりにつはらかにいはむ。」
(現代語訳)「内町の新町にある。その由来ははっきりとはわからないが、人々の語る話に基づいて、旭塚について詳しく述べよう。」
このように、旭塚の伝承の朝日の神子と、内町の新町にあったという神女境内とは関連があるように記録しています。朝日の神子は「みこやしき」に居た巫女かと思われます。尚、内町の新町は横手川による浸食(川欠け)で移転しています。
黒丸惟孝
黒丸惟孝(これたか)は黒丸家7代目当主で、藩への貢献から郷士となり名字帯刀を許されるなど、角間川町に貢献した記録の残る人物です。新町の稲荷神社の項の黒丸家の人です。権斎塚も惟孝が建てています。
菅江真澄
江戸時代後期の紀行家・民俗記録者。宝暦4年(1754)三河国に生まれ、各地を旅しながら、その土地の風景や人々の暮らし、風俗・伝承を自らの文章と挿絵で克明に記録しました。特に東北地方に長く滞在し、秋田では藩に招かれて地誌の編纂にも関わりました。その記録は現在、民俗学や歴史学の貴重な資料として高く評価されています。
菅江真澄と雪の出羽路
菅江真澄の『雪の出羽路・平鹿郡』は、文政7年(1824)から文政12年(1829)にかけて編纂されました。この地誌編纂は、真澄が秋田藩の援助を受けて正式に取り組んだものです。真澄は自らの足で平鹿郡(現在の横手市周辺)を巡り、村々の景観、風俗、信仰、伝承などを詳細に記録しました。文章には和歌や随筆を織り交ぜ、挿絵も多く添えられており、当時の暮らしや文化を今に伝える大変貴重な歴史資料となっています。
参考文献
- 秋田叢書刊行会編「雪出羽道・上」『秋田叢書第5巻』秋田叢書刊行会、1933年、pp.104-113。
- 大曲市昔を語る会連絡協議会『大曲市の歴史散歩』大曲市・大曲市昔を語る会連絡協議会、1977年、pp.100-119。